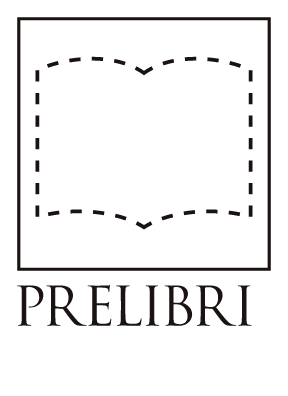10月のフラジャイル博覧会に登場してくれる森田春菜さん。FRAGILE BOOKSでは2024年5月の「あわいもん」でご一緒させていただきました。この度、満を持して個展の開催が実現。焼きたての本について、ご本人からお話をお聞きました。
<展覧会情報>
Baked Book
by Haruna Morita
期間:2024年10月1日〜10月31日
場所:FRAGILE BOOKS|オンライン展示室を見る
Baked Bookというタイトルになりました。
森田さん ———「焼き加減」について櫛田さんと話しているときに、どこで成功と失敗の判断をしているかと聞かれて出た言葉が「おいしそう」だったんです。例えば、ご飯だったら炊きたての一粒一粒がキラキラ輝いてツブ立っている感じかなぁという話しになって、もう少し「かたち」に寄せて言うと、「窓を開けた途端に風でカーテンがフワッとはためく瞬間」を留めたかたちが良いな、と。
その「フワッとはためく一瞬のかたち」は計画的に作れるものですか?
森田さん ———最終的にどんなかたちに仕上がるかは、焼いてみないとわかりません。ある程度は和紙に含ませた泥漿(でいしょう:粘土と水を混ぜ合わせて泥のような液体状にしたもの)が乾燥する際に収縮するので、その収縮率を感覚的にコントロールすることで予測はできるんですけど、それはあくまでも経験値によるもので、実際はその日の気候や空気中の湿度などにかなり影響されます。
焼いている途中に、中の様子を見たりできますか?
森田さん ———パンのように低温ではなくて、1200度や1300度の世界なので、窯の中は覗けても、眩しすぎて中身の状態を確かめることはできません。窯に入れたら冷めて出すまで、どんなかたちになるかは見えないです。ただ、私の場合は、すべてをコントロール出来て、思い通りのかたちを作れる、となったら、それはそれで作為的な部分や「我」が全面に出てきてしまいそうで、かえって壊したくなるか、別な方法を探したくなるかもしれません。
「うつわ」などは、森田さんはあんまりやらない。
森田さん ———必要にかられて作ることもありますが、大学生の頃からすでに素材の質感や造形そのものに惹かれていたこともあり、いわゆる実用品としての「うつわ」は私の表現言語としてしっくりくるものではないと思っています。私のつくるものは、自己表現を前面に押し出して完成させるのではなく、素材との相互作用によって生まれてくるという感覚なんです。
たしかに、作家モノにありがちな手癖はあまり感じない。
森田さん ———そう言われるのは、うれしいです。私の作りたいものたちは、もちろん私が作ったものだから人工物なんですが、できればかたちも質感も、もともとその姿を持って生まれてきたかのように、置かれる環境や見る人にとって、自然に溶け込むような存在であって欲しいと願っています。
その方向性はいつから意識し始めたのでしょう。
森田さん ———割と早かったと思いますが、大学二年生頃には「心地よい」と感じる質感を自覚しはじめていました。ちょうど骨董屋や古道具屋にも通い始めていて、いろいろなものを見て触って得た感覚がありました。私が好きなのは、古いものの哀愁でも客観的な価値でもなくて、物質が時間と共に変化を遂げることでした。変化が面白くて好きなんです。流行りを作為的に取り込むことにも、抵抗があります。本の世界で言えば、平台に積まれる雑誌やベストセラー小説ではなくて、陽の当たらない本棚で百年に一度風を受けるのを待っている分厚い一冊みたいな。わたしは時代を超えて共感される書物を書きつづけたいタイプなんです、きっと。その一冊が在ることに意味や幸福感を感じるような、そんな作品と、その周りの空気をつくりたいと思っています。
今回の「Baked Book」も時間と共に変化しますね。
森田さん ———この「Baked Book(ベイクド・ブック)」は、はじめから経年変化を意識してつくったシリーズで、こんな風につくります。まず和紙の表面に泥漿を塗って、それを板に並べて乾燥させます。乾燥した紙片を素焼きすると、和紙の表情が転写された薄い磁土片ができます。それと同時に和紙も焼けて消えてしまいます。釉薬をかけずに焼成するので、むき出しになった銀は空気中の硫黄に反応して、表面の色が徐々に変化していきます。数年待たずとも古紙を束ねたようになることもあります。焼きたての姿はそのままで、どんどん色が変わっていく様子もぜひ楽しんでいただければと思います。
私たちは、こわれやすいものを多く扱っていますが、森田さんの作品はその中でも飛び抜けてフラジャイルです。
森田さん ———空気に触れているだけで変化するほどですからね。でも、手に持った時の感覚と見た目のギャップもこの作品の魅力なので、実際に手にとってみていただきたいです。